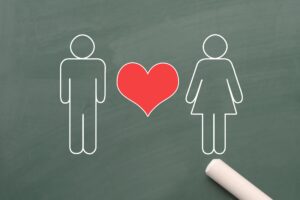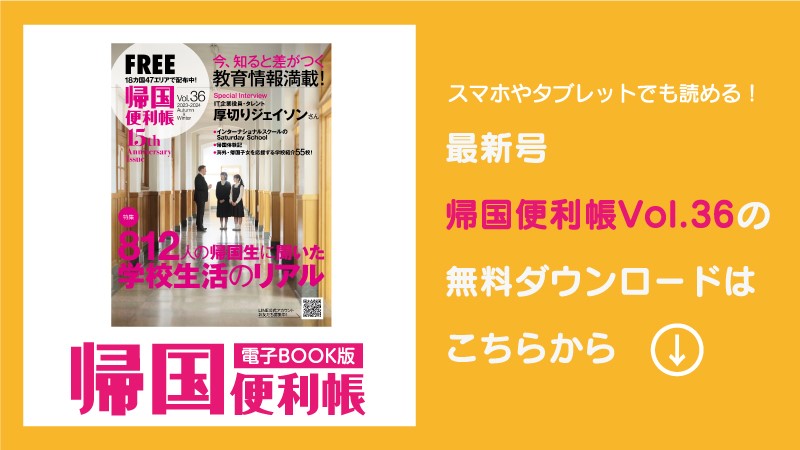これからの時代を生きるうえで大切なことは、異文化や個々の多様性を理解し、それぞれの良さを活かしながら共存することだ。ただ、頭ではわかっていても、自分が周囲の人と違っていると悩んだり、自分らしさを発揮することを躊躇している人は少なくない。そこで、日本でTOEIC Programを実施・運営する一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)は、まだ思考が凝り固まっていない若い世代を対象に、<あなたの「明日」を変えるトークイベント~Kizashi~>を開催(2020年2月15日、東京都江東区の日本科学未来館7F未来館ホールにて)。第2回目となる今年は、さまざまな境界を越えて活動している5名が登壇。彼らのスピーチの一部を紹介する。
海外へ飛び出す夢や日本人に見えないことへの悩みを率直に語る

宮澤かれん(みやざわ・かれん)さんは、小笠原諸島の母島で育ち、高校を卒業後、一般社団法人HAND STAMP ART PROJECT(※病気や障がいを抱える子どもとそれを支え応援する人々の手形や足形を集め、世界一大きな絵を描くことを目指すプロジェクト)の海外特派員として、ハンドスタンプを集めるため単独世界一周に出発した。いつか海外に出てみたいと思っていた宮澤さんは、高校生の頃にオーストラリアへ留学したが、帰国後、クラスメイトが進路を決めている中、自分は何も決まっていないことに焦りを感じたという。「自分は何をしたいのか」と悩んでいたとき、父親に「もし余命1年だったら何をしたい?」と聞かれ、ぱっと浮かんだ答えが、単独世界一周だったそうだ。若者が夢や目標を見つける過程を素直に話した宮澤さんは、「毎朝ワクワクして起きて、夜は“いい1日だった”と眠る。そんな風に毎日を大事にして、今を生きていきたい」と結んだ。

日本人の母親とクロアチア人の父親との間に生まれた玉利ドーラ(たまり・どーら)さんは、クロアチア内戦により日本に逃れた体験を持つ。高校時代から給付型奨学金を探してドイツやオランダなど8か国に滞在し、さまざまな国籍、年代、職業の人々と共に暮らした。現在はNPO法人WELgeeで、日本に逃れた難民のサポートを行っている。彼女はハーフであることから、外国人のように見える女性が日本社会で働くことの悩みを吐露した。例えば、母親とは日本語で話していたけれど敬語に自信がなく英語での仕事しかできないと思い込み、前職で英語教師をしていたこと。就職試験で面接官に8か国の滞在歴を「自由だね。それで何がしたいの?」と言われてしまったこと。外見を気にして天然パーマの髪をぴったりと結び、日本人らしく見せようとしていたこと。悩んだ末に、「仕事がないかなら自分で作ればいいんだ。日本人と外国人の良い関係を築くためのサポートをしよう」と前向きに捉えられるようになったそうだ。
日本型の学校を設立して祖国ネパールに恩返し
 NPO法人YouMe Nepal代表理事&CEOのシャラド・ライさんは、ネパールの農村部に生まれ育ち、小3のときに社会の教科書で日本という国の存在を知ったという。高校卒業後、奨学金を得て立命館アジア太平洋大学(APU)に留学。留学中、ふと小学校の同級生は何をしているのか気になってインターネットで調べたところ、何人かとSNSでつながることができたが、誰ひとりとして高校を卒業できず海外へ過酷な出稼ぎ労働に出ていたことを知った。自分との境遇の差に愕然としたライさんは、せめて彼らの子どもたちを助けたいと思い立つ。そこで、APU在学中に、ネパールで日本型教育を教える学校<YouMe(夢)School>を設立。「日本の学校の良いところは、時間を守ること、自分たちで教室の掃除をすること。それを取り入れています」と話すライさん。「設立時はお金も経験もなかったけれど、あれこれ考えていたら始められなかった。設立した学校に子どもたちが笑顔で通っている姿を見るとうれしい。人に笑われない夢は大きな夢とはいえない。たとえ自分の夢を笑われることがあっても、心から望んでいることは目に見えない力、“宇宙全体”が協力して叶えてくれるんです」と笑顔で聴衆に語りかけた。
NPO法人YouMe Nepal代表理事&CEOのシャラド・ライさんは、ネパールの農村部に生まれ育ち、小3のときに社会の教科書で日本という国の存在を知ったという。高校卒業後、奨学金を得て立命館アジア太平洋大学(APU)に留学。留学中、ふと小学校の同級生は何をしているのか気になってインターネットで調べたところ、何人かとSNSでつながることができたが、誰ひとりとして高校を卒業できず海外へ過酷な出稼ぎ労働に出ていたことを知った。自分との境遇の差に愕然としたライさんは、せめて彼らの子どもたちを助けたいと思い立つ。そこで、APU在学中に、ネパールで日本型教育を教える学校<YouMe(夢)School>を設立。「日本の学校の良いところは、時間を守ること、自分たちで教室の掃除をすること。それを取り入れています」と話すライさん。「設立時はお金も経験もなかったけれど、あれこれ考えていたら始められなかった。設立した学校に子どもたちが笑顔で通っている姿を見るとうれしい。人に笑われない夢は大きな夢とはいえない。たとえ自分の夢を笑われることがあっても、心から望んでいることは目に見えない力、“宇宙全体”が協力して叶えてくれるんです」と笑顔で聴衆に語りかけた。
夢を叶えるまでの苦悩や気付きを共有

バラが好きな田中綾香(たなか・あやか)さんは、20歳のときに農家に弟子入りし、2015年、22歳でROSE LABO株式会社を設立した。自社農園で農薬を使わない「食べられるバラ」を栽培し、バラを加工した食品や化粧品の開発などを手掛けている。2017年には、GSEA(Global Student Entrepreneur Awards:Entrepreneurs’ Organizationが主催する学生起業家を対象としたアワード)の日本代表にも選ばれている。そんな田中さんは、「幸せになるために私が大切にしていることは3つあります。選択肢を広げること。自分の弱さを受け入れること。家族や友だちとの時間を大切にすること」と語り始めた。具体例として、会社を経営する中で感じた自分の弱さを挙げた。それは計画性のなさであったといい、改善するにはどうしたらよいかできるだけ多くの選択肢を考え、その中でベストと思われることを実行していったそうだ。また、“仕事”を免罪符に家族や友人との時間をないがしろにしていた時期もあったといい、それでは幸せになれないことを感じたという。田中さんが大切にしている“3つのこと”は、多くの人にとって幸せに生きるためのヒントになりそうだ。
 栗山龍太(くりやま・りょうた)さんは、11歳のときに緑内障により失明、さらに両親の離婚により児童養護施設で育った。筑波大学理療科教員養成施設を卒業後、横浜市立盲特別支援学校職員として働いているが、ミュージシャンとして成功する夢もあきらめてはいない。過去にはCDデビューも果たしたが、音楽会社の事情ですぐに終了してしまったという。「そんなある日、パラリンピック出場を目指していた生徒から、『先生、くさっていないでパラリンピックのための曲を作ってみたら?』と言われたんです。彼女は『パラリンピックという特別な場所があるから輝くことができる』と言いました。僕はそれまで、障がい者だけで競うのではなく健常者に勝ってこそ認められると思っていましたが、それは自分がどこかでまだ障がいを受け入れられていなかったからだということに気付いたんです」と思いを語った。生徒の言葉を機に、パラアスリートを励ます曲「リアルビクトリー」を製作、自費でリリースし、音楽活動を再開した。最後に、盲導犬アンジーの横で自作の歌を熱唱し、会場を盛り上げた。
栗山龍太(くりやま・りょうた)さんは、11歳のときに緑内障により失明、さらに両親の離婚により児童養護施設で育った。筑波大学理療科教員養成施設を卒業後、横浜市立盲特別支援学校職員として働いているが、ミュージシャンとして成功する夢もあきらめてはいない。過去にはCDデビューも果たしたが、音楽会社の事情ですぐに終了してしまったという。「そんなある日、パラリンピック出場を目指していた生徒から、『先生、くさっていないでパラリンピックのための曲を作ってみたら?』と言われたんです。彼女は『パラリンピックという特別な場所があるから輝くことができる』と言いました。僕はそれまで、障がい者だけで競うのではなく健常者に勝ってこそ認められると思っていましたが、それは自分がどこかでまだ障がいを受け入れられていなかったからだということに気付いたんです」と思いを語った。生徒の言葉を機に、パラアスリートを励ます曲「リアルビクトリー」を製作、自費でリリースし、音楽活動を再開した。最後に、盲導犬アンジーの横で自作の歌を熱唱し、会場を盛り上げた。
登壇者の現在の活動よりも、そこに至るまでの悩みや乗り越え方など内面にスポットを当てた今回のトークイベント。自分らしく生きたいと願うすべての人々にとって、刺激や支えになったのではないかと思う。
※登壇者のトーク動画を3月下旬公開(予定)。IIBCのページにYouTubeのリンク有り
写真提供/一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会(IIBC)
(取材・文/中山恵子)

-e1583916045173.jpg)